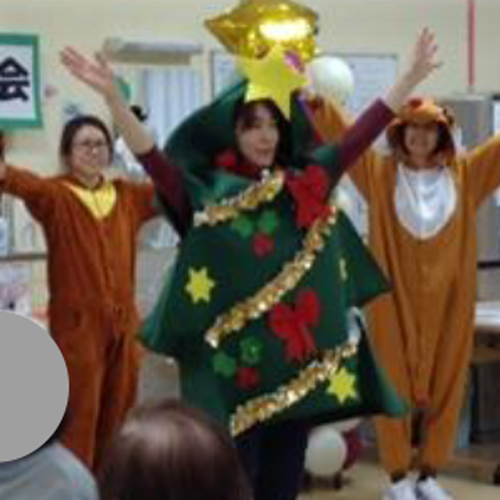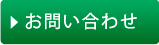| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| デイサービス | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| デイケア | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リハビリ・入浴も体験できます。
体験時の昼食代は無料です。
施設長 コラム 「廃用症候群とは?」 文責:小出弘寿
今月のコラムは、「廃用症候群」についてお話しします。皆さんは、廃用症候群という言葉を聞いたことはありますか?医療・介護職の方であればよく聞く言葉ではあると思いますが、一般的にはあまり聞きなれない言葉だと思います。今回は、そんな廃用症候群についてご紹介しようと思います。
廃用症候群とは、長期間の安静や活動量の低下によって、身体機能や精神機能が低下する状態を指します。
要は「使わないことで失われる」状態です。特に高齢者とっては、以下の3つの理由で廃用症候群になりやすいです。
①筋力や体力の低下が早い:高齢者は加齢によって筋力や骨密度が低下しています。そのため、数日間の安静でも著しく筋力が落ちてしまいます。
②基礎疾患の影響:脳梗塞、骨折、肺炎などによる入院や安静がきっかけで活動量が急減し、廃用症候群を引き起こすことがあります。
③精神的影響:長期間の寝たきりは、うつ症状や認知機能の低下も招きやすくなります。
そして、これら3つの理由などで廃用症候群を呈すると、結果として、筋萎縮や関節拘縮、起立性低血圧、骨粗鬆症、心肺機能低下、認知機能低下、うつ状態、便秘・食欲不振、褥瘡(床ずれ)などの症状を認めることになります。
高齢者に対する廃用症候群の予防は、早期離床とリハビリが重要です。具体的には、関節を動かす運動やストレッチ、座る・立つなどの訓練、栄養管理、家族やスタッフとのコミュニケーションによる精神的サポートが大切です。高齢者は、調子を崩すと体力の回復までに時間がかかるため、あまり動きたくない気持ちも理解できますが、動かさないことが廃用症候群を引き起こしてしまうため、私たち医療や介護の現場では、「安静にしすぎないこと」は重要なキーポイントなのです。もし、何らかのきっかけで廃用症候群を呈してしまった場合は、当介護施設の通所介護、通所リハビリ、訪問リハビリ、訪問看護なども有効に活用して下さればと思います。