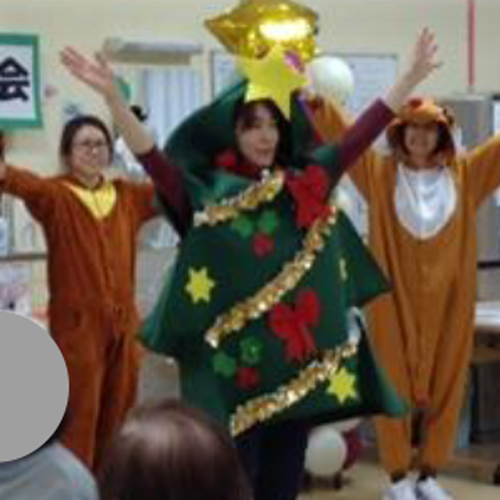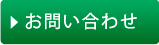| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| デイサービス | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| デイケア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リハビリ・入浴も体験できます。
体験時の昼食代は無料です。
施設長 コラム 「難聴と認知症」 文責:小出弘寿
今月のコラムは、「難聴と認知症」の関係についてお話ししようと思います。難聴と認知症の関係は、近年の研究で非常に注目されているテーマですので、今回は、わかりやすくポイントをまとめてみました。
①難聴は認知症のリスク因子
難聴は、認知症の発症リスクを高める要因の一つとされています。特に中年期(40~60代)における難聴は、後年の認知症リスクを上げることが明らかになっています。
②どうして難聴が認知症につながるの?
いくつかの仮説がありますが、今回は3つお伝えします。
●脳の刺激が減る:耳からの情報が減ると、脳への刺激も減り、認知機能が低下しやすくなります。
●社会的孤立:会話がしづらくなり、人付き合いが減ることで、うつや孤立が進行し、認知症のリスクが高まります。
●脳の負荷増加:聞き取りにくい音を理解しようとすることで、脳が余計な労力を使い、他の認知機能に使う脳の力を労費させてしまいます。
③対策はあるの?
●補聴器の活用:補聴器の使用によって、認知機能の低下を遅らせる可能性があるという研究結果も出ています。
●定期的な聴力検査:40代以降は、定期的な聴力チェックを行い、早めの対処が重要です。
●社会参加の維持:難聴があっても、できるだけ人と話す機会や趣味活動を続けることが、脳に良い刺激となります。
耳が聞こえにくいと感じる方は、耳鼻咽喉科で難聴の評価を受けてみることが大切です。また、必要があれば補聴器を試してみるのも有効です。今の補聴器は、機能やデザインが優れている物がたくさんありますからね。